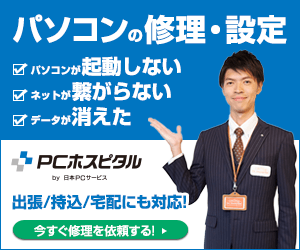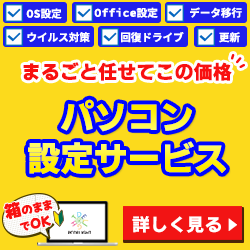PCのファン回転数を上げる方法を探している方に向け、仕組みと設定手順を体系的に整理しました。回転数上げるメリット・デメリットや回転数目安の考え方、PCファンのおすすめ回転数は何か、用途別の回転数設定の基本、PCのファンを最適化するにはどうすればいいか、そしてファンが回りっぱなしの原因は何かまでを網羅します。さらに、回転数を上げるBIOSの手順、windows10と11のファン回転数確認手順、ノートPCのファン強制回転の可否、静音化のために回転数を下げるポイント、最後にPCのファン回転数を上げるまとめまで一連の流れで解説します。本文は客観情報に基づき、個人的体験は含めません。
- 回転数を上げるべき状況と副作用の理解
- BIOSやユーティリティでの具体的設定手順
- Windowsでの回転数や温度の確認方法
- ノートPCでの可否と代替策の選び方
PCのファン回転数を上げる基礎

- 回転数を上げるメリット・デメリット
- 回転数の目安の考え方
- PCファンのおすすめ回転数は?
- 用途別の回転数 設定の基本
- PCのファンを最適化するにはどうすればいいか?
- ファンが回りっぱなしの原因は?
回転数を上げるメリット・デメリット

ファン回転数を引き上げる判断は、単なる「うるさくなるかどうか」では測れません。PCの冷却は、CPUやGPUが出す熱量(ワット)を、ヒートシンクやラジエータを経由して空気に放出する「熱移動のボトルネック」をどれだけ減らせるかで決まります。回転数を上げれば単位時間あたりに押し出す空気の体積(風量)と、ヒートシンクのフィン間を押し通す力(静圧)が増し、結果として放熱効率が高まります。空冷ではサーマルスロットリングの発生を抑止しやすくなるため、アプリケーションのフレームレートやレンダリング時間が安定しやすい傾向があります。たとえばIntelはデスクトップ向けCPUについて、最大でおおむね100℃付近まで動作設計され、温度が上がれば自動的にクロックを制御する仕組みを案内しています(参照:Intelサポート)。AMDもRyzen 7000シリーズなどで90〜95℃付近を制御目標にする設計があると説明しています(参照:AMD公式コミュニティ記事)。高温域での制御余裕を作るという観点でも、適切なシーンでの回転数引き上げは有効です。
技術的な背景を補足すると、産業分野でよく用いられる「ファン法則(Affine Law)」では、風量は回転数にほぼ比例し、静圧は回転数の二乗に比例、そして入力動力は回転数の三乗に比例すると説明されます(参照:Odell Associates(ファン法則)、AMCA Fan Acoustics Whitepaper)。つまり、ほんの少し回転数を引き上げるだけでも、フィン詰まりの強いラジエータや高密度ヒートシンクへ空気を押し込む力が大きく改善します。一方で、騒音は単純比例ではなく増え方が急峻になりやすく、心理的な「うるささ(騒音の知覚)」はスペクトル(音の成分)にも左右されます。トーン成分の強いファンは同じデシベルでも耳障りに感じられることが多く、ベアリングや羽根設計の品質が体感差を生みます(参照:Noctua:PWMと制御の解説)。
デメリット面では、まず騒音の増加が挙げられます。ファンの音は一般に回転数に応じて上昇し、さらに乱流や共振が重なると帯域によっては急激に耳に触るピークが現れます。ケースのパネルやシャーシに伝わる微振動も体感ノイズの一部です。次にファン自体の摩耗です。ベアリングにはスリーブ、ライフル、流体動圧(FDB/HDB)、ボールなどの方式があり、品質や使用姿勢(水平・垂直)、温度によって寿命が変わります。代表例として、高品質な流体動圧系ベアリングを採用するNoctuaの多くのモデルはMTBF(平均故障間隔)15万時間以上を公表しています(参照:Noctua製品ページ、NoctuaデータシートPDF)。ダブルボールベアリングの名作として知られるNidec Servo GentleTyphoonは35℃で10万時間のMTBFが示されています(参照:QuietPC製品仕様)。高回転の常用はベアリング負荷や塵埃の侵入リスクを高めるため、必要時に上げ、不要時には下げるというカーブ運用が寿命面の観点でも合理的です(一般的なベアリング特性解説:be quiet! 技術記事、Digi-Key TechForum)。
さらに見落とされやすいのが、ケース内のエアフロー設計との相互作用です。吸気と排気のバランスが崩れていると、回転数を上げても循環ループ(ホットエアの再循環)が起き、期待ほど温度が下がらないことがあります。前面・底面からの整流された吸気、背面・天面からの効率的な排気という「気流の矢印」を揃えるだけで、同一回転数でもコア温度が数℃程度下がる事例は珍しくありません。フィルターの目詰まり、グラボの排気方向、ケーブルの取り回しなど物理的な要因を点検してから回転数を上げると、最小の騒音増で最大の温度低下を狙えます。
ハードウェア側の温度制御仕様にも触れておきます。多くのGeForce GPUでは、ブースト制御の都合上、80℃台前半〜後半付近で自動的にクロックが調整される設計が広く見られます(参照:NVIDIA Developer Forum)。CPU/GPUともに「仕様の範囲内」でも、温度マージンが広いほどクロック維持の余裕が増すため、目的(静音・性能・寿命バランス)に応じてファンカーブで上げ下げを使い分けることが重要です。
高回転=常に安全ではありません。PCケース内の吸気・排気のバランス(エアフロー)が悪いと、回しても温度が下がらない場合があります。まずは吸気と排気の流れを点検し、フィルターやヒートシンク、通気口の清掃を行ってから調整してください。データセンター向けの指針では、入気温度や湿度管理の重要性が強調されますが、一般PCでも「吸気空気の質」を整える発想は有用です(参照:ASHRAE Thermal Guidelines)。
要点の整理:回転数を上げると風量・静圧が増え、温度余裕と性能安定性の確保に寄与します。一方で騒音と摩耗は増えるため、PWM制御で必要時のみ上げる設計が理にかないます。ベアリング品質とケース内エアフローを整え、「上げる前に整える」が最短の近道です。
回転数の目安の考え方
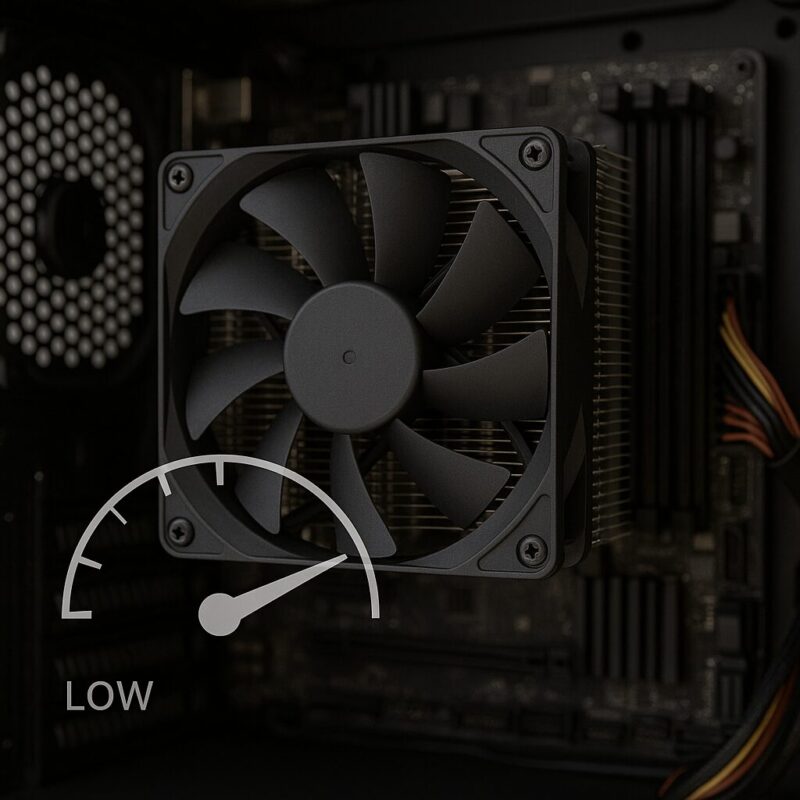
数値目安は「何RPMが正解か」ではなく、温度目標に対して必要な風量・静圧をいかに最小騒音で確保するかという設計の結果として決まります。まず把握したいのは、主要パーツがどの温度帯で安定動作しやすいかという基礎情報です。一般にデスクトップ向けCPUは90〜100℃付近に保護制御の上限があり(IntelとAMDの公式解説にその旨が示されています:Intelサポート/AMDコミュニティ)、GPUも80〜90℃台でブースト制御が働く設計が広く見られます(参考:NVIDIA GPU Boost)。ただし仕様上限は安全の境界であって目標温度ではありません。余裕温度(マージン)を確保するほど動作クロックの維持や部品周辺の熱ストレス低減につながるため、実運用ではもう少し低い範囲で管理するのが一般的です。
温度目標を先に決める
筆者視点ではなく、一般的な推奨としては次のような「温度基準の目安」が広く採用されています。室温30℃を想定する夏場、アイドル〜軽負荷はCPU35〜50℃、重負荷時は70〜80℃程度に収まるカーブをまずは目指します。GPUはアイドル40〜55℃、重負荷時70〜83℃程度を当面の目標とし、NVMe SSDはサーマルスロットリングが発生しやすい70℃前後を超えないようにヒートシンクやケース風を当てます(SSDの温度仕様はベンダーで差があるため、メーカーFAQなど公称範囲を参照してください)。
| デバイス | アイドル目安 | 重負荷目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU(デスクトップ) | 35〜50℃ | 70〜80℃ | 仕様上限は90〜100℃帯(参照:Intel/AMD) |
| GPU(ゲーム/演算) | 40〜55℃ | 70〜83℃ | GPU Boostが温度依存、83℃付近を目安に |
| NVMe SSD | 30〜45℃ | 60〜70℃ | 70℃超でスロットリング事例、製品仕様を要確認 |
| VRM/メモリ | — | 80〜95℃以下 | VRMは熱に強いがケース風の確保が重要 |
回転数の決め方は「カーブ」で考える
温度目標が決まったら、ファンの回転数は「単一値」ではなく温度—回転率の関係(ファンカーブ)として設計します。PWM制御(4ピン)は低速域の安定性に優れ、細かな閾値設定に向きます。DC制御(3ピン)は電圧で調整するため極低速域が不安定になりやすく、最小回転が高めに張り付くケースがあります。どちらもBIOS/UEFIやユーティリティで「最小デューティ」「停止閾値」「応答速度(ランプアップ/ランプダウン)」の設定を持つことが多く、ここを詰めると体感が大きく改善します。
設計の勘所:ヒステリシス(上げ下げで別の閾値にする)や応答遅延を入れると、瞬間的な温度変動でファンが小刻みに鳴く「ハンチング」を抑制できます。静音重視なら、低温域の傾斜を緩く、高温域で一気に立ち上げるのが定石です。
サイズ別・用途別のRPM起点
同じ風量でも、140mmは120mmより低RPMで達成しやすく静音に有利です。240/360mmラジエータの水冷も静圧型ファンの採用で低RPM運用に余地が生まれます。一般的な起点として、120mmファンはアイドル600〜900RPM、軽負荷900〜1200RPM、重負荷1300〜1700RPM、140mmはそれぞれ100〜200RPMほど低い設定から試すやり方が見られます。とはいえケースやヒートシンクの通風抵抗で必要静圧が大きく変わるため、騒音許容の範囲で段階的に詰めてください。
室温と季節の補正
PCは室温の影響を強く受けます。一般論として内部温度は室温+7〜10℃程度高くなりやすく、夏季は目標温度に届きにくくなります。夏用・冬用の二つのプロファイルを作っておくと、季節の変化に柔軟に対応できます。電源プラン(Windowsのバランス/高パフォーマンス)や、アイドル時のバックグラウンドタスクも温度基準に影響するため、カーブ調整時は常に同一条件で計測することが大切です。
騒音の感じ方はデシベル値だけでなく周波数成分に依存します。ブレード先端の乱流や軸受の唸りが耳障りなピークを生む場合があり、同じRPMでもファンの銘柄で体感が大きく違うことがあります。スペックで「最大騒音値」が低い製品でも、実際のピークが苦手帯域にあると不快に感じられるため、カーブ設計と併せて製品選定が重要です(参考:AMCA Fan Acoustics)。
PCファンのおすすめ回転数は?

「おすすめ回転数」は万能の正解ではありません。ケースの通風抵抗、ヒートシンク密度、ラジエータ厚み、ダストフィルター、グラボの排気方向、室温、さらには個々のファンのP-Q特性(静圧—風量曲線)が異なるため、同じRPMでも得られる風量と騒音が大きく変わるからです。そこで本節では、サイズ別・用途別に「起点」となるゾーンを示し、調整手順と検証指標を明確にします。
サイズ別の起点RPMゾーン
| ファンサイズ | 静音重視の起点 | バランスの起点 | 冷却重視の起点 | 想定 |
|---|---|---|---|---|
| 120mm | 600〜900RPM | 900〜1200RPM | 1300〜1700RPM | 空冷CPU/240mm水冷/ケース |
| 140mm | 500〜800RPM | 800〜1050RPM | 1200〜1600RPM | 大型空冷/360mm水冷/ケース |
| 92mm/80mm | 800〜1100RPM | 1100〜1500RPM | 1600〜2200RPM | SFF/トップフロー/小型ケース |
水冷ラジエータはフィン密度(FPI)と厚みで必要静圧が変わります。高FPI・厚ラジは同風量でも静圧が不足しやすく、静圧型ファンをやや高めのRPMで回す必要があります。逆に薄型・低FPIなら低RPMでも十分に冷えることが多く、静音性を取りやすい構造です。
カーブ調整の手順(実測ベース)
1)測定環境を固定:室温、電源プラン、側板の開閉、フィルター清掃状態を統一します。2)アイドル測定:OS起動5分後のCPU/GPU/SSDの温度と各ファンRPMを記録。3)軽負荷測定:Web会議や軽い編集など「日常作業」を10分程度再現。4)重負荷測定:Cinebenchやゲームベンチ、GPU負荷ツールなどで15分以上。5)調整:アイドル域は耳で気にならないRPMまで下げ、中温域(CPU50〜70℃付近)からの勾配で目標温度に届くよう段階を付けます。6)再測定して温度・騒音・ファンの上下動(ハンチング)を確認します。
温度はセンサー位置で差が出ます。CPUのTctl/TdieやGPUのホットスポットは他の表面温度より高めに出ることがあり、どの指標を基準にカーブを動かすかを統一してください。マザーボードの「マザボ温度」や「VRM温度」をトリガーに使える機種もあります。
騒音と快適性の測り方
スマートフォンの騒音計アプリは絶対値が不正確な場合がありますが、相対比較には十分使えます。A特性(dB(A))で、アイドル時35〜38dB、軽負荷40〜42dB、重負荷45〜50dB程度を目安にすれば、多くの室内環境で気になりにくいレンジに収まります。特定の周波数ピークが耳障りな場合は、RPMをわずかに上下させて共振帯を外すのが有効です。
よくあるつまずき
- 低速域でファンが停止→「最小デューティ」か「ファンストップ機能」を確認
- 温度は下がらないのに騒音だけ増える→吸排気のバランスやケーブル整流を見直し
- 一部ファンだけ高回転→センサー割り当てがCPU/GPU以外(PCH/VRM)になっていないか確認
なお、公式サイトではPWM制御や軸受に関する資料が提供されており、制御の基礎理解に役立ちます(参照:Noctua:PWM解説)。
用途別の回転数 設定の基本

用途に応じた「温度—騒音—寿命」のバランス設計が、日々の満足度を左右します。静音性が最重要のワークスペースと、フレームレート安定を第一とするeスポーツ、長時間のエンコードやレンダリングで熱累積が起きやすい制作現場では、最適なカーブの形が変わります。本節では、代表的な3パターンを示し、それぞれの設計ポイントを整理します。
① 静音最優先(学習・執務・録音)
狙いは「低温域の沈黙」。CPU45〜55℃、GPU50〜60℃までは可能な限り低RPMに抑え、ヒステリシスと応答遅延で微小な温度揺れによるファン上下動を抑えます。ケースは140mmファン主体で低回転を許容し、前面吸気にフィルターを使う場合は定期清掃で圧損の増加を防ぎます。水冷ならラジエータ面積を確保し、ラジファンは静圧型を低RPMで運用。録音・配信などノイズにシビアな用途では、ファンストップ(低温時停止)も選択肢ですが、停止/始動時のトーン変化が気になる場合は最小RPMを保つ方が耳障りが少ないことがあります。
② バランス重視(一般ゲーム/軽い編集)
中温域(CPU55〜70℃、GPU65〜78℃)からカーブの勾配をやや急にし、短いピークに素早く反応させます。ケースの前面・底面に吸気、背面・天面に排気を置く基本配置を徹底し、グラフィックスカードの吸気側へ新鮮な風が届くようケーブルを整えます。グラボのファンカーブはベンダーツールで個別調整が可能な場合があり、ケースファンのカーブと同期させると温度の追従が素直になります。
③ 性能最優先(eスポーツ/長時間エンコード)
温度の急上昇に備え、CPU/GPUの中温域から積極的に風量を投入します。VRMやメモリ、NVMeにも気流を当てると、熱ダレやスロットリングによる性能低下を抑えられます。長時間負荷ではケース内の平均温度が数十分かけてじわじわ上がるため、初期の温度だけを見て回転数を控えめにするのは非推奨です。30分以上の連続ベンチや実業務ワークロードで再検証し、温度上振れを織り込んだカーブを作成してください。
| 方針 | 低温域(〜50℃) | 中温域(50〜70℃) | 高温域(70℃〜) | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 静音 | 20〜35% | 35〜55% | 60〜80% | 遅延・ヒステリシスで安定化 |
| バランス | 25〜40% | 50〜70% | 75〜90% | ケース/グラボの同期が有効 |
| 性能 | 30〜45% | 65〜85% | 90〜100% | 熱累積を見込んで早めに増速 |
小型フォームファクター(SFF)の特記事項
ITXケースやスモールケースは吸気/排気の自由度が低く、小径ファンを高回転で回す場面が増えます。吸気口の直近にダストフィルターがある構造では圧損が大きく、フィルター清掃の有無で温度が数℃変わることも。正圧(吸気多め)にすると漏れからの吸い込みダストが減り清掃頻度を抑えられますが、排気不足で内部に熱がこもることがあります。逆に負圧は排気が強く温度は下がりやすい反面、隙間からダストを吸いやすくなります。ケース構造と設置環境に合わせ、実測で有利な方を選択してください。
PCのファンを最適化するにはどうすればいいか?

最適化の本質は「計測→整備→設計→検証」の反復です。回転数を上げる前に、まず熱の抜け道を整えることで、同じ騒音でより低い温度を実現できます。以下の手順は、一般ユーザー向けに再現しやすいよう標準化した流れです。
1. 計測:現状の見える化
温度・RPM・負荷をモニタできるツールを用意します。OS標準だけでは足りないため、マザーボードのユーティリティや一般的なセンサー読み取りツールを利用します。確認すべきは、CPU温度(Tdie/Tctl)、GPUコア温度とホットスポット、各ファンRPM、VRMやPCH温度、NVMe温度です。アイドル/日常作業/重負荷の3段階で10〜30分ずつ記録し、温度の立ち上がり方と安定値を把握します。
2. 整備:物理的ボトルネックの除去
- 通気口とダストフィルターの清掃(圧損低減)
- ヒートシンクのフィン間の埃除去(放熱面積の回復)
- ケーブルの束ね直し・裏配線で整流
- 前面/底面吸気、背面/天面排気の基本配置確認
- NVMeやVRMへのスポット風確保(ケースファン角度や位置の工夫)
これだけで同RPMでも温度が数℃下がる事例は珍しくありません。古いサーマルグリスは劣化して熱伝導が落ちるため、必要に応じて高性能グリスへ交換します(メーカーが推奨する交換周期や塗布ガイドに従ってください:例 Noctuaの塗布ガイド)。
3. 設計:ファンカーブの作成
BIOS/UEFIまたは純正ユーティリティで、温度目標に沿ったカーブを作成します。最小デューティ(停止しない最低回転)、ファンストップ(低温時停止)、応答遅延、ヒステリシスを調整し、ハンチングを抑えます。可能ならデバイス別のトリガー(CPU温度でCPUファン、GPU温度でケースファン等)を設定します。グラボはベンダーツール(例:NVIDIAのツールやボードメーカーのユーティリティ)で個別調整できる場合が多く、ケース排気のカーブをGPUに連動させるとホットスポット抑制に効果的です。
4. 検証:温度と騒音の両面で評価
ベンチマークや実作業を30分以上回し、温度の上振れ、RPMの変動、耳に触るピークの有無を確認。夏用・冬用プロファイルや「静音・バランス・高冷却」の3プロファイルを保存しておくと、用途に応じてワンタッチで切り替えられます。Windowsの電源プラン(バランス/高パフォーマンス/省電力)も温度に効くため、プロファイルとセットで管理するのが実務的です。
補助策:ケースファンの口径を拡大(120→140mm)/フィルターの目の細かさを見直し(高密度は静音と引き換えに圧損増)/ラジエータ厚みやFPIに合った静圧型ファン採用/ダクトや遮蔽物の撤去など小改良で、回転数を上げずに温度を下げる道が開けます。
ファンが回りっぱなしの原因は?

原因は「実際に熱い」か「制御の都合で回している」の二系統に大別できます。前者は負荷や埃、エアフロー不良など物理的要因、後者はセンサー値の読取り、電源プラン、プロファイル設定、BIOS仕様など論理的要因です。切り分けは次の順で進めると効率的です。
ステップ1:負荷と温度の実測
タスクマネージャーでCPU/GPU/ディスク使用率の高止まりを確認し、バックグラウンド更新、インデックス作成、同期アプリ、マルウェア走査などを疑います。温度モニタでCPU/GPU/SSDが高温維持なら「実際に熱い」ため、次の物理要因を確認します。
ステップ2:物理要因の洗い出し
- ダストフィルターやヒートシンクの詰まり
- 吸排気の逆配置や遮蔽物(ケーブル、HDDトレイ)の影響
- 室温の上昇(エアコン設定や設置環境)
- グラボの排気熱がCPU吸気側に回り込む構造
- サーマルグリス劣化、クーラーの取り付け圧不足
ステップ3:論理要因(制御)の点検
- 電源プランが高パフォーマンス固定でアイドルクロックが高い
- マザボ・GPUユーティリティのプロファイルが常時パフォーマンス
- センサー割り当てミス(PCH温度などでケースファン全開)
- BIOSの最小デューティ設定が高すぎて低速域に下がらない
- ファンストップ機能無効、または最小回転閾値未調整
ノートPCは構造上、小型ファンを高速回転させる前提の設計が多く、「回りっぱなし」が仕様の場合があります。メーカー提供ユーティリティでのカーブ調整や電源モード切替が主な対処で、サードパーティでの強制制御は保証や安定性に影響する可能性があります。メーカーのサポート情報を優先してください。
ステップ4:改善の優先順位
優先度は、清掃→電源プラン見直し→プロファイル切替→カーブ再設計→物理改修(ファン位置/本数/口径)→サーマルグリス交換の順が実務的です。これで改善しない場合、センサー異常やファームウェア不具合の可能性があり、BIOS更新やサポート窓口での診断が有効です(更新はメーカー指示に従い、リスクを理解して実施してください)。
「高回転=冷えない」は整流不足のサインです。風は通りやすい方へ逃げるため、ヒートシンクやラジエータのコアを貫通させるには静圧と流路設計が必要です。ファンを増設しても逆効果のことがあるため、吸気2・排気2(または吸2排1)の基本から、温度と騒音の実測で最適点を探してください。
PCのファン回転数を上げる手順
- 回転数を上げる biosの手順
- windows10/11 ファン回転数の確認手順
- ノートPCのファン強制回転の可否
- 静音化のために回転数を下げる
- ノートPCのファン回転数を上げるまとめ
回転数を上げる biosの手順

BIOS/UEFIには、CPUファンやケースファンを温度に応じて制御するための項目が用意されていることが一般的です。ここではメーカー非依存の汎用手順をベースに、各社が用意する呼称や機能名も併記しながら、安全に回転数を上げるまでの流れを整理します。なお、用語としてBIOSとUEFIが併用されますが、現在はUEFIが主流です。マザーボードの世代やモデルにより画面構成は異なるため、詳細は必ず取扱説明書を確認してください(参照:ASUSサポート/MSIサポート/ASRockサポート/GIGABYTEサポート)。
1. UEFIへ入る(Windowsからの手順も可)
電源投入時にDeleteキーまたはF2キーでUEFIに入るのが通例です。Windows 10/11環境では、設定→システム→回復→「今すぐ再起動」→トラブルシューティング→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定→再起動でもアクセスできます(参照:Microsoft サポート:Windowsの回復オプション)。
2. ハードウェアモニタ/ファン設定画面を開く
「Hardware Monitor」「Monitor」「Q-Fan」「Smart Fan」などの項目を探します。ここでCPU温度、各ファンの回転数(RPM)、電圧、ポンプ回転などが一覧表示されます。編集対象のヘッダー(CPU_FAN、CHA_FAN1/2、AIO_PUMPなど)を選択します。
| メーカー例 | UEFI上の機能名例 | 付属ユーティリティ |
|---|---|---|
| ASUS | Q-Fan Control/Q-Fan Tuning | Armoury Crate/Fan Xpert(参照:FAQ) |
| MSI | Hardware Monitor(Smart Fan Mode) | MSI Center(参照:MSI Center) |
| ASRock | FAN-Tastic Tuning/Fan Tuning | A-Tuning(参照:A-Tuning) |
| GIGABYTE | Smart Fan 5 | GIGABYTE Control Center(参照:GCC) |
3. PWM/DCの選択と最小回転の把握
ファンのコネクタ形状により制御方式が異なります。PWM(4ピン)はデューティ比で細かく制御でき、低速域の安定に優れます。DC(3ピン)は電圧制御のため極低速が不安定になることがあります。UEFIで自動判定(Auto)を選ぶか、接続方式に合わせて明示選択します。次に「最小デューティ」や「ストップ温度」を調整し、停止せずに回り続ける最低回転(セーフミニマム)を特定します。
4. 温度—回転率のカーブを編集
カーブ編集では、低温域の傾斜を緩く、中〜高温で一気に傾斜を付けると静音性が得られます。例としてCPUは45℃まで25〜35%、60℃で50〜60%、70℃で75〜85%、80℃で100%といった段階が分かりやすい始点です。ケースファンはCPU温度だけでなく、マザーボード温度やVRM温度をトリガーに選べる機種もあり、長時間負荷での熱だまりを避けるのに有効です。
5. チューニング機能の活用と保存
ASUSのQ-Fan Tuningなど、ファンの特性を自動測定して最小回転を見つける機能が用意されている場合があります。自動チューニング後でも、目標温度に合わせて手動で微調整し、プロファイルを保存(例:Silent/Balanced/Turbo)しておくと用途ごとに切替えやすくなります。
注意:UEFIの設定変更は、条件次第で起動不良の原因になります。変更前に初期設定のスクリーンショットやプロファイル保存を行い、万一に備えましょう。更新(BIOSアップデート)はメーカー手順に従い、停電・中断対策のうえ実施してください(参照:Microsoft:ドライバー/ファームウェア更新の基本)。
6. 検証:温度・騒音・挙動の安定性
OS起動後に温度監視ツールでアイドル・軽負荷・重負荷を順に確認し、温度の上振れ・ファンの小刻みな上下(ハンチング)・共振による耳障りな帯域がないかチェックします。必要に応じて「応答遅延」「ヒステリシス(上げ下げの閾値差)」を加え、実環境に馴染むカーブへ整えます。なお、GPUはボードメーカーのツールで個別にカーブ調整可能なことが多く、ケース排気ファンのカーブをGPU温度に合わせるとホットスポットの抑制に役立ちます。
windows10/11 ファン回転数の確認手順

Windows 10/11には、ファン回転数を直接表示する標準機能は基本的にありません。そこでセンサー読み取りツール(マザーボード付属ソフトや汎用モニタリングツール)を用い、温度・回転数・負荷を同時に観測します。以下は、一般的な確認フローです。公式ツールやベンダー配布ユーティリティを優先的に使用すると、センサー名の対応が正確でトラブルが少なくなります(参照:ASUS/MSI/GIGABYTE/ASRock)。
確認フロー(基本)
①マザーボードのユーティリティ(Fan Xpert/MSI Center/Smart Fan等)をインストール→②ソフトを起動し、CPU/GPU/マザーボード温度、各ファンRPMの表示を有効化→③アイドル時の値を数分観測し記録→④動画再生やブラウジングなど軽負荷での変化を記録→⑤ゲームやレンダリングなど重負荷での最高温度・RPMを記録→⑥UEFIまたはユーティリティのカーブを調整→⑦再度①〜⑤を繰り返し、目標温度と騒音のバランスに近づけます。
Windows側の影響:電源モードが「高パフォーマンス」だとアイドル消費が増え温度が上がりやすく、結果として回転数も上がります。設定→システム→電源の電源モードを「バランス」へ、バックグラウンドアプリの自動起動を見直すことも有効です(参照:Microsoft サポート)。
よくある表示上の注意点
- 「CPUファン」と「ポンプ(AIO_PUMP)」を取り違えない
- ケースファン(CHA_FAN)の番号と実配線の対応をメモしておく
- 温度センサーの名称(Tdie/Tctl、PCH、VRM、System等)を揃えて比較する
- GPUはボードメーカーのユーティリティで個別にRPMが読める
これらを踏まえて観測すれば、どの温度がトリガーでどのファンが上がっているかの因果関係が分かり、無駄な高回転を見つけやすくなります。
ノートPCのファン強制回転の可否
ノートPCは筐体の容積・通風経路・騒音要件を総合的に最適化する設計であり、ユーザーが任意のRPMに強制固定できない場合が少なくありません。理由は、安全設計・騒音規格・電池寿命・ファームウェア制御が密接に結び付いているためです。多くのメーカーは、パフォーマンス/バランス/静音などのモード切替のみを公開し、個別のカーブ編集はクローズドにしています(例:Lenovo Vantage、ASUS Armoury Crate、HP Command Center)。
現実的な対処(許容範囲内で)
- 電源モードの適正化:Windowsの電源モードをバランスへ、メーカーのパフォーマンスモードを状況に応じて切替
- 吸気口の清掃:ファン開口部とヒートシンクの埃詰まりを除去(メーカーの分解ガイドに従う)
- 冷却台の活用:底面吸気を補助するクーラーパッドで温度マージンを確保
- 高負荷の平準化:ゲームでフレームレート上限を設定、可変解像度やアップスケーラ(DLSS/FSR)で発熱を抑制
注意:サードパーティ製ツールによる強制制御は、機種によっては挙動不安定や保証の対象外となる可能性が指摘されています。メーカーが提供する設定の範囲内で調整し、最新のBIOS/ECアップデートが配布されていれば適用可否をサポート情報で確認してください。
また、薄型機では小径ファンを高回転で回して熱を逃がす設計が一般的で、「回りっぱなし」に見える挙動が仕様のことがあります。耳障りな帯域が問題であれば、ファンのオンオフよりも電源モード・室温・設置面の見直し(柔らかい布やベッドの上を避け、硬く通気の良い面に置く)が効果的です。
静音化のために回転数を下げる
静音化は単純に回転数を下げるだけでは達成できません。重要なのは、「同じ温度を、より低いRPMで達成する」ための一連の対策です。以下は、効果と副作用、実装のしやすさを考慮した現実的な手順のセットです。
段階的アプローチ
- 整備(清掃・整流):ダストフィルター、ヒートシンク、ケーブル取り回しを最適化
- 口径・枚数の見直し:120mm主体から140mm主体へ、吸気/排気のバランスを再設計
- 静圧型ファンの採用:フィルターやラジエータ越しでも風を通す
- ファンカーブ最適化:低温域の傾斜を緩く、ヒステリシスや応答遅延でハンチング抑制
- 発熱源への対処:CPUのPL制限や電圧最適化、GPUのフレーム上限設定
| 対策 | 静音効果 | 温度への影響 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| フィルター清掃 | 中 | 低〜中の改善 | 圧損低減で同RPMでも風量増 |
| 140mm化 | 高 | 中の改善 | 取付互換とクリアランス要確認 |
| 静圧型ファン | 中 | 中〜高の改善 | フィン密度/フィルター越しで有効 |
| カーブ再設計 | 高 | 状況依存 | 低温域は緩く、高温域で素早く |
| PL/電圧最適化 | 高 | 高の改善 | パフォーマンス影響を要評価 |
| フレーム上限 | 中 | 中の改善 | 体感の滑らかさと要バランス |
温度マージンを過度に削るのは推奨されません。CPU/GPUともに仕様上限付近での運用はブースト維持や周辺部品の熱ストレス面で不利になるため、目標温度からの余裕(5〜10℃程度)を確保するのが無難です(参照:Intelサポート:CPU温度の一般指針/NVIDIA:GPU Boost)。
注意:ファンストップ機能は静音に有効ですが、停止・再始動時の音の変化がかえって気になる場合があります。最小RPMを設定して常にごく低速で回しておく運用も選択肢です。VRMやNVMeなどケース風に依存する部位の冷却も忘れないでください。
PCのファン回転数を上げるまとめ
PCの最適化とファン運用の要点を、実践時に見返しやすい形で整理しました。以下のチェックリストを用い、温度と騒音のバランスを客観的に評価してください。
- 温度目標を先に決めファン回転数はカーブで設計する
- PWMとDCの違いを理解し4ピン接続を優先して使う
- 清掃と整流で同じ回転数でも冷却効率を底上げする
- 夏冬や用途別にプロファイルを複数保存して切替える
- 低温域は緩やかに中高温域で素早く回転数を上げる
- 応答遅延とヒステリシスでファンのハンチングを抑える
- ケースは前面底面吸気と背面天面排気の基本を守る
- 140mmや静圧型の採用で低RPMでも風量と静圧を確保する
- Windows電源モードを見直しアイドル消費を抑制する
- GPU側はフレーム上限設定で発熱をコントロールする
- ノートPCはメーカー提供モード内で調整を優先する
- 強制固定回転は機種依存であり保証範囲を確認する
- VRMやNVMeの温度も観測しスポット風を検討する
- 温度と騒音は必ず実測し同一条件で比較評価する
- 仕様上限付近の常用は避け温度マージンを確保する